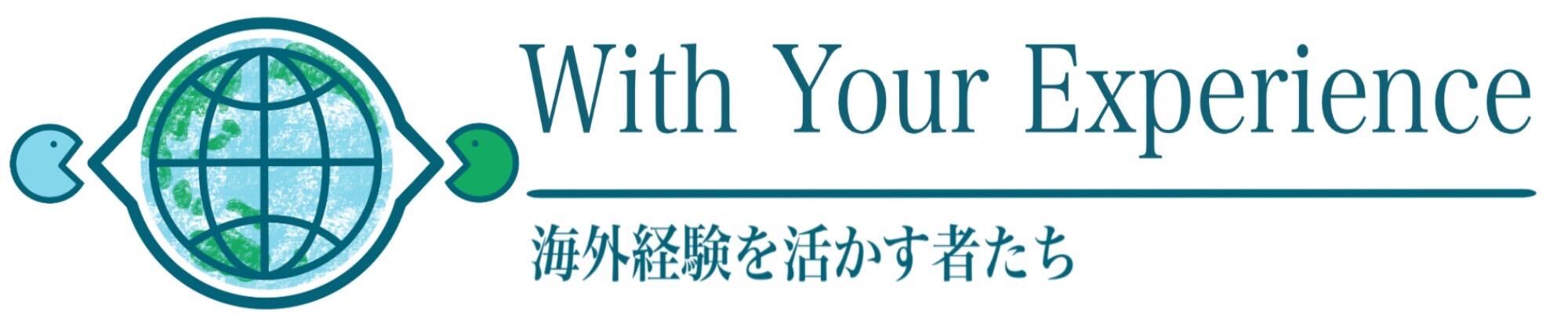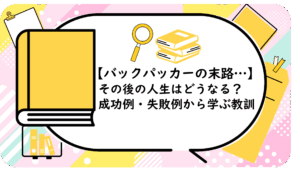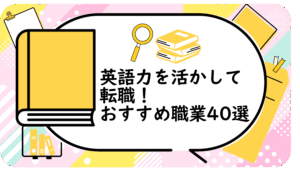「平凡な人生を変えたい」その一心で海外へ──挫折と再挑戦の先に見つけた新しいキャリア
人生について疑問を感じ、オーストラリアへの挑戦から始まった旅。フィリピン留学で英語を磨き、帰国後は介護職を経て、英語を活かす道としてIT業界へ。経験を重ねるごとに、自分の可能性を広げていきました。
石黒 潤紀さん
“このままでいいのか”が、すべての始まりだった──平凡な日常を抜け出し、人生を変える旅へ。

学生の頃から、英語にはなんとなく興味はありました。洋楽とか、洋画が好きで。だからあの頃の自分にとって、英語は“憧れの国の言葉”みたいな存在でした。
高校を卒業してからは地元の短大へ進み、経済学を専攻しました。でも正直、真面目な学生ではなかったと思います。授業は最低限出て、バイトして、なんとなく過ぎていく毎日。今振り返ると、特に何かを成し遂げたわけでもなく、ただ「卒業した」という事実だけが残った2年間でした。
社会人になって最初に働いたのはパチンコ店です。最初に内定をもらった会社にそのまま入りました。職場には個性の強い人が多くて、毎日がちょっとしたドラマみたいでした。楽しくはあったんですけど、ふとした瞬間に「自分はこのままでいいのか?」と考えるようになったんです。何か、もっと大きなことをやってみたい。そう思ったとき、頭に浮かんだのが“海外”でした。
どうせやるなら、とことんやってみよう。そう考えて選んだのが、オーストラリアへのバックパッカー旅です。「何もない場所で自分がどこまで通用するのか」を試したかった、見知らぬ土地で、自分の足だけで立ってみたかったんです。映画で観たバックパッカーの姿にも、どこか憧れがありました。
初めての海外。ケアンズ、ブリスベン、シドニー…と、地図をなぞるように転々としました。特別な計画はなく、「とりあえず行ってみよう」という気持ちだけで。
でも現実は厳しかったです。英語は全然話せず「なんとかなるだろう」で飛び込んだ自分の甘さを痛感しました。マクドナルドで注文が通じず、店員に怪訝な顔をされたときは、本当に落ち込みました。外に出るのが怖くなって、宿にこもる日もありましたね。「自分は何をしてるんだろう」って。
それでも、旅先で出会った人と過ごした時間は、今でも鮮明に覚えています。シドニーのタワーから一緒に見た夕日。あの瞬間は、ちゃんと旅をしている気がしました。
結局、2週間ほどで帰国。思い描いていた“バックパッカーの旅”にはほど遠く、悔しさばかりが残りました。でもその悔しさが、次への原動力になったんだと思います。「絶対リベンジする」、そう心に決めて。
もう一度、海外で通用する自分へ──挫折から始まった“再挑戦の旅”

オーストラリアから帰ってきたあと「このままじゃ終われない」という気持ちがずっと心のどこかにありました。あの悔しさを晴らしたくて、アルバイトを掛け持ちしながらお金を貯めて、次の挑戦に備えていました。
そして25歳の頃、踏み出したのがフィリピンへの語学留学です。目的は明確で、「海外で通用する自分になること」。バックパッカーとして旅をする前に、まずはちゃんと英語を話せるようになりたかったんです。
フィリピンを選んだのは、いくつか理由がありました。まず費用が安かったこと。カナダやオーストラリアに比べると、かなり現実的な金額で留学できる。もう一つは、人からのすすめでした。以前バックパッカーをしていた知り合いが「フィリピンは英語の勉強にすごくいい」と教えてくれたんです。
選んだのは人気のあるセブ島ではなく、バコロドという田舎町。日本人が少なくて、落ち着いた場所がいいなと思ったんです。観光地の喧騒よりも、静かに、自分のペースで勉強できる環境を求めていました。
フィリピンの語学学校はマンツーマン授業が中心で、逃げ場がない(笑)。話さざるを得ない環境に自分を置いたのは正解でしたね。
もともと文法とかアカデミックな英語は苦手だったので、先生にお願いしてフリートーク中心にしてもらいました。だんだんと自然な会話のなかで、少しずつ言葉が出てくるように。滞在は2ヶ月ほどでしたが、終わる頃には一人で出かけても怖くないくらいの英語力がついていました。マクドナルドでもちゃんと注文できる(笑)。ゼロからのスタートを思えば、大きな進歩でした。
そして語学学校を終えたあと、いよいよ本来の目的だったバックパッカーの旅へ。とはいえ、想定以上にお金を使ってしまっていたので、世界一周ではなく東南アジアを中心に周ることにしました。タイ、ラオス、カンボジア。半年ほどかけて、ゆっくりと各地を巡りました。
旅のスタイルは、“移動より滞在”。一つの場所に腰を据えて、現地の人たちと同じように生活するのが好きでした。ドミトリーに泊まって、出会った人たちとご飯を食べたり、お酒を飲んだり。特別な観光地よりも、そういう“なんでもない時間”のほうが印象に残っています。
半年の旅を終えて帰国したときは、正直、燃え尽きていました。ずっと憧れていたことをやりきった達成感と、ぽっかり空いたような感覚。
日本に帰ってきても、同年代の友人たちはもう社会人としてしっかり働いていて、「自分はこの社会に戻れるのかな」と不安もありましたね。
しばらくアルバイトをして、少し落ち着いた頃、介護の仕事に出会いました。実際に働いてみると、これが思っていたよりずっとやりがいがあって。お年寄りの方に何かをしてあげたとき、「ありがとう」と笑顔で言ってもらえる。それだけで救われるような気持ちになりました。旅とは違うけれど、“人と向き合う”という意味では、根っこの部分はつながっているのかもしれません。
介護からITへ──“英語を活かしたい”想いが導いたキャリアチェンジ

介護の仕事は、約3年続けました。
やりがいはありましたが、腰を痛めてしまって。体力的にこの先も続けていくのは難しいかもしれない、と思い始めた頃でした。ちょうどその頃、フィリピンで身につけた英語力をもっと活かしたいという気持ちもまた湧いてきていたんです。「このままでいいのか」と自問するようになり、転職を決意しました。
次に選んだのは、IT業界。介護とはまったく違うように見えますが、不思議と抵抗はなかったですね。介護の現場で人を見てきた経験と、ITでネットワークを“見る”という仕事は、実は通じる部分があると思っていました。対象が人間かシステムかの違いであって、根っこは「問題を見つけて解決する」こと。そこに本質的な違いはない気がしたんです。
新たな会社へ入社後は、ネットワークを監視する業務を担当しました。ネットワークの障害を検知したら、お客様へ報告し、障害が継続する状態のときにはベンダーとやり取りをして修理し、原因を追う。3年間、ひたすらトラブル対応の毎日でした。
一番大変だったのは、お客様とのコミュニケーション。ITの知識がない方にもわかるように噛み砕いて説明しなければならないですし、状況報告についての判断力も求められます。言葉の選び方ひとつで相手の受け取り方が変わる――その難しさを実感しました。この時期に“相手目線で伝える力”がかなり鍛えられたと思います。
技術的にも、サーバーやルーター、スイッチ、ファイアウォールなど、ネットワークの基礎を幅広く学びました。今でも「困ったら再起動」という教訓は忘れられません(笑)。問題の切り分け方や冷静さは、仕事だけでなく、日常生活にも役立っています。
3年経った頃、統括というポジションに移りました。現場全体を見渡して、最終判断を下す立場です。チームの動きを見て、「あ、手が止まってるな」「困ってそうだな」と気づいたら声をかける。みんなが安心して動けるように、空気を読むことを大切にしていました。プレッシャーは大きかったけれど、チームを支える面白さも感じていました。
その後は、サービスマネージャーとして新しい案件の立ち上げを担当。実際の運用というより、運用設計や契約内容の整理など、これまで触れてこなかった分野の仕事でした。文書化や調整業務に苦労しながらも、「現場だけでは見えなかった仕組みの裏側」を知る貴重な経験になっています。
振り返ると、海外での経験も少なからず今の仕事に影響しています。知らない環境に飛び込んで生き抜いたことで、「初めてのこと」に対する抵抗がなくなったんです。たとえわからないことがあっても、「まあ、なんとかなるか」と思えるようになりました(笑)。
今後は、これまでの経験を活かせるような現場で、より広い視野を持って働いていきたいと思っています。
海外へ行こうと思っている人へアドバイスをお願いします
不安なこととか怖いこととかあると思いますけど、後悔せずに、思い切ってチャレンジしてみてください!